| 曲目解説 |
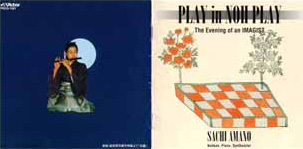
|
||
|
これらの曲の原型は、笛、小鼓、大鼓、太鼓で演奏される能楽囃子であるが、能管の音は西洋音階に合わないので、旋律 をそのまま受け入れている訳ではないし、また原型には和音がない。それらのことを考慮すると、ここに提示されたのはイメ ージの信号の変換のようなものである。原曲を知っている人には、あの曲のあの部分だとわかるところもあるかもしれない。 ユーモアまたは知的な遊びであり、本歌取りのようなイメージのひろがりを楽しむ世界である。 1. プロローグ 能管の調べ「お調べ」演奏者が舞台に出る前、楽器の調子を調べ、これから演奏する曲の雰囲気の位取りをする。 「名のり」この旋律にのって、はじめにこの世と異界への仲介者が登場してきて、名をなのる。 2. 龍の出現(Harp) 原曲「早笛」Hayafueは、怨霊や龍神、武士等が急調子で勢いよく登場する時の曲である。ここでは 能「竹生島」の龍神を想定しているが、原曲より比較的ゆっくり波を蹴立てて進んでくるイメージ。 3. ヴォカリーズ 鶴(Chapel Choir, Harp) 和歌の浦に潮満ちくれば片男波 芦辺をさしてたづ鳴きわたる(山辺赤人)ー この和歌を歌詞とした原曲のヴォカリーズ。 4. ヴォカリーズ 鵲( Chapel choir, Jazz Vibes) かささぎのわたせる橋に置く霜の 白きを見れば夜ぞふけにける(大伴家持)ー この和歌を歌詞として、民俗芸能の「鷺舞」の旋律を用いた原曲のヴォカリーズ。 5. 鼓の舞(Chapel Choir, Piano) 原曲「羯鼓」Kakkoは僧形の遊行者の舞。腰に羯鼓という鼓をつけ、撥で打ちながら舞う軽妙な曲。 能楽囃子は八拍子であり、また日本音楽には三拍子がないといわれているが、この原曲には三拍子の痕 跡があると推察される。 6. 酒好きの妖精の舞(Goblin, Jazz Vibes) 原曲「猩々乱」Shojo midare。猩々は海に棲み、酒を好む想像上の動物。足の運びと旋律が独特であ り、ここではGoblinが猩々の雰囲気を彷彿とさせる。 7. 夢の庭(Harp, Orch.Hit) 原曲は「出端」Dehaという登場楽に続いて、「早舞」Hayamaiという男性貴族、龍女などの舞う曲。 ここでは能「融」を想定している。平安貴族源融の幽霊が廃墟に現れ、趣向を凝らしていた昔日の庭を 偲んで舞う。 8. シャーマンの舞(Taiko, Ocarina, Warm pad) 原曲「神楽」Kaguraは、女神や神前で舞う巫女の曲であるが、その笛の旋律を太鼓の音に変換してあ る。 9. 超自然の登場(Techno Pad, Goblin) 原曲「大癋穵從beshiは、天狗や魔神の登場楽。Goblinは天狗のユーモラスな味、Techno Padは のっしのっしと歩く感じが出ている。 10. 水辺曲(violin, Harp, Orch .strings) 原曲「盤渉楽」Banshikigaku。 楽には黄鐘調(f)調と盤渉(h)調があり、盤渉調は高い音の旋律パターンをとる。 また盤渉調は水に関係のある場合に用いられ、能「菊慈童」では、山中に棲む菊の精が菊の葉に置く露からできた清 流の側で舞い、能「天鼓」では、湖に沈められた鼓の名人の少年の幽霊が舞う。 11. 魂の飛翔(能管、piano) 原曲「翔」Kakeriは、成仏しない武士や、子供をなくした母親、恋に狂った人などが、狂おしく舞台をさまよう時の 旋律。「かけり」とは魂が空中を翔るという意。 12. 顕現(Chapel Choir, Acous.Bass, Orch.Strings, piano, 能管) 原曲「獅子」Shishi 。 能「石橋」においては、深山の橋を渡ろうとした僧の前に現れた獅子が、牡丹の花に戯れ遊ぶ 様を表している。 獅子はこの世界に顕現したパワーの象徴であり、獣の持つ怪しさ、神聖さ、美しさをも表す。 序の部分はChapel Choir, クルイと呼ばれる部分は能管、Orch.Stringsと楽器を変えて、繰り返し獅子が登場する様 を表し、原曲とはちがったとぼけた味がある。 13. An Ensemble (能管、木管フルート:竹内祐子、ピアノ) 能管新曲のための記譜法による作品。西洋音階に合わない能管と木管フルートのかけあい。ピアノは手が空いている方 が弾いている。(3+5) /8拍子はハムザ・エル・ディンの曲のタールのリズムより借用。異質な出自の二管の「ある調 和」を求めた遊びである。
|
||